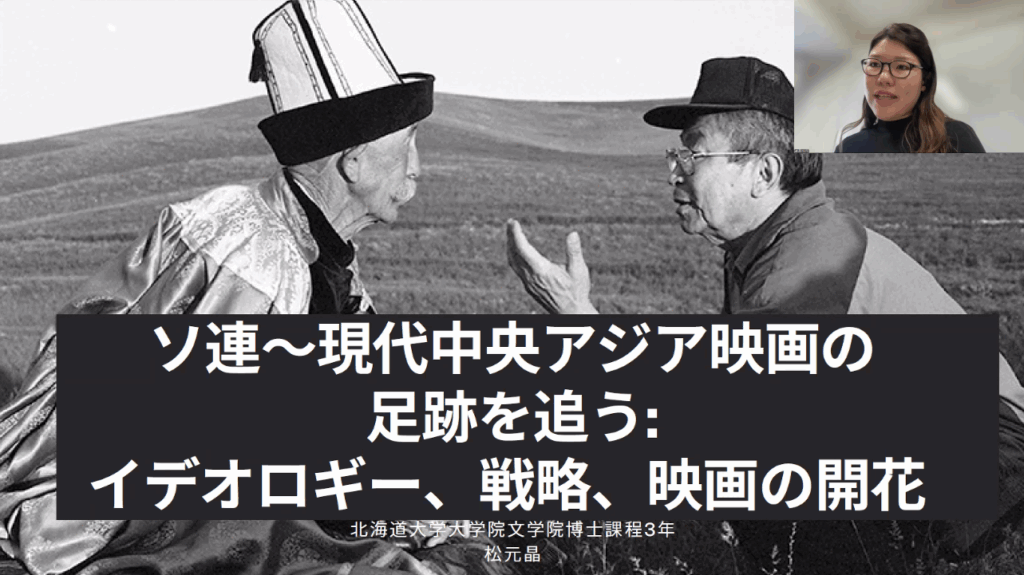2025年2月27日(木)、第53回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催し、北海道大学大学院文学院博士課程3年の松本晶氏をお招きして、「ソ連~現代中央アジア映画の足跡を追う:イデオロギー、戦略、映画の開花」と題する講演をしていただきました。
2025年2月27日(木)、第53回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催し、北海道大学大学院文学院博士課程3年の松本晶氏をお招きして、「ソ連~現代中央アジア映画の足跡を追う:イデオロギー、戦略、映画の開花」と題する講演をしていただきました。
松元氏は、ソ連映画の研究をされています。2019年~2022年、在カザフスタン日本国大使館の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」で委嘱教員として勤務する傍ら、資料調査を通じカザフスタン映画とのつながりを形成。現在は1960年代のカザフスタン・クルグズスタン・ウズベキスタン映画に焦点を絞り、映画に現れる表象とその背景、映画人の活動を調査していらっしゃいます。
中央アジア映画は、他国・他者との比較でアイデンティティを確立するのではなく、ロシア中心主義や文化的なヒエラルキーがあることも認識したうえで、そうした複雑な背景を利用して映画を製作してきた歴史があります。また、ソ連において映画は最も重要な芸術とされ、イデオロギーを浸透させる役割を担っていました。それらの点に注目して、今回の講演では、中央アジア映画とイデオロギーの関係、表象の変化と社会的背景、また中央アジア映画人たちの活動についてお話しいただきました。
中央アジア映画の始まりは1908年と意外に早く、当初から映画が政治的力を持つと確信されていました。1920年代には伝統批判、女性の解放、革命的思想などソ連映画の潮流をうけた作品が多く制作されました。一方で、中央アジアはソ連映画の中で「非文明的な存在」として描かれることが多く、例えば「トゥルクシブ(Turksib)」という映画では、ステレオタイプ的な考えや中央アジアを非文明であることが如実に描かれているそうです。
1930年代は、後にウズベク映画の礎といわれるほど、映画文化が発展していきます。戦時中は疎開してきたロシア人から技術的・演技的指導を受け、映画製作がさらに進展しました。戦後の1960年代にはソ連映画の再興とともに、カザフスタン・クルグズスタン・ウズベキスタンといった各国でも映画が発展していきます。特にクルグズ映画は国際的にも人気が高かったようです。
1980年代には、ペレストロイカの影響により、より自由な表現が可能となります。そして1990年のソ連崩壊とともに、ソ連映画全体が「何を作るべきか」というアイデンティティの喪失に直面したという歴史全体の流れにそってご説明いただきました。
このように、中央アジア映画は、歴史の流れと連動しながら、ソ連のイデオロギーに対して適応・批判・利用といった柔軟な対応を続けてきました。常にソ連中央の動向を注視しつつ、その枠組みの中で映画芸術を発展させながらも、それぞれの国に抱かれるステレオタイプを打破しようとする姿勢が見て取れるとお話しいただきました。
質疑応答では、カザフスタンにおける大衆映画と歴史映画について、1955年代になぜ女性は芸術映画を製作できないといわれていたのか、現在のロシア映画における中央アジアの位置づけについての質問がよせられました。