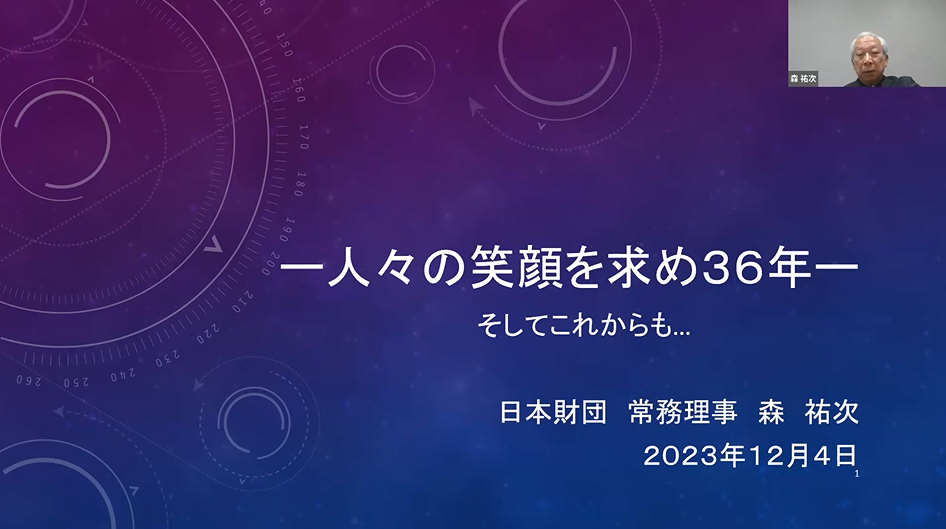2023年12月4日(月)、第44回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。今回は、NipCAプロジェクトを財政面をはじめ多様な形で温かくご支援してくださっている公益財団法人日本財団の常務理事、森祐次氏を講師にお招きして、「人々の笑顔を求め36年:そしてこれからも……」と題する講演をしていただきました。
2023年12月4日(月)、第44回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。今回は、NipCAプロジェクトを財政面をはじめ多様な形で温かくご支援してくださっている公益財団法人日本財団の常務理事、森祐次氏を講師にお招きして、「人々の笑顔を求め36年:そしてこれからも……」と題する講演をしていただきました。
本講演では、36年間にわたりさまざまな非営利活動団体を率いて世界各地の地域課題の改善と解決に人生を捧げてこられた森氏より、これまでのご活躍について、貴重な知見や現地でのユニークなエピソードを交えて詳しく語っていただきました。お話は、前職での経験を通じ、非営利活動団体での活動がご自身に適していると感じて活躍の場を移されたところから始まります。森氏がこれまでに主に所属された団体とそこでの主な活動内容は以下のとおりです。
・笹川平和財団で、アジア諸国の農村開発NGOなどを支援する。
・医学の専門知識を活かして自然災害や紛争の被災者を支援するNGO「アジア医師連絡協議会(AMDA)」で、世界各地の被災者や難民の支援などに携わる。
・日本緊急救援NGOグループ(JEN)の事務局長として、旧ユーゴスラビア紛争の難民支援活動に尽力する。
・日本環境財団において、ソ連からの独立後10年を経たモンゴル社会の現状を体感しつつ、モンゴルの自然環境改善に向けた活動を推進する。
・ICA文化事業協会にて、アジア・アフリカ・中南米の農村開発事業などに携わる。
・モンゴル国公益法人「ワンセンブルウ・モンゴリア」を設立し、モンゴル伝統医療の普及事業などを展開する。
・日本財団国際協力グループ長として、主に東南アジア・中央アジア・中南米・アフリカを舞台に、基礎教育や公衆衛生、農業技術の向上、人材育成、平和構築などを支援する。
森氏はどの団体においても、困っている人に可能な限りの支援の手を差し伸べることと、国際協力分野で後進人材を発掘、育成、支援することを常に大切にされてきたとのことです。
そして、このような多岐にわたるご活躍を通じて実感された重要な姿勢を9つ、参加者にもお伝えいただきました。それは、①社会公益活動をするときは常に社会で起こる事象に好奇心を持つこと。②世界的視野を持ち常に自分の立ち位置を客観的に見ること。③現場主義に徹すること。④どのような状況にあっても常に初心に戻り、活動の目標を見失わないこと。⑤文化、社会、宗教など、さまざまな面での「通訳者」になること。⑥自分の活動分野の仲間や人的ネットワークを維持拡大すること。⑦自分の信念は柔軟に貫くこと。⑧常に自分のスキルと活動実績について棚卸しをして自分のセールスポイントを把握しておくこと。⑨急いで離職すると次の仕事を探す際に自分を安売りすることになるので、離職するときは次の仕事を決めてから今の組織を離れること、とのことです。
異なる文化圏において直面した多種多様な課題とその解決に向けた具体的な取り組みをお話しいただき、NipCAプロジェクト、さらには筑波大学の今後の発展に生かすことのできる数多くのヒントを学ばせていただいた講演会でした。