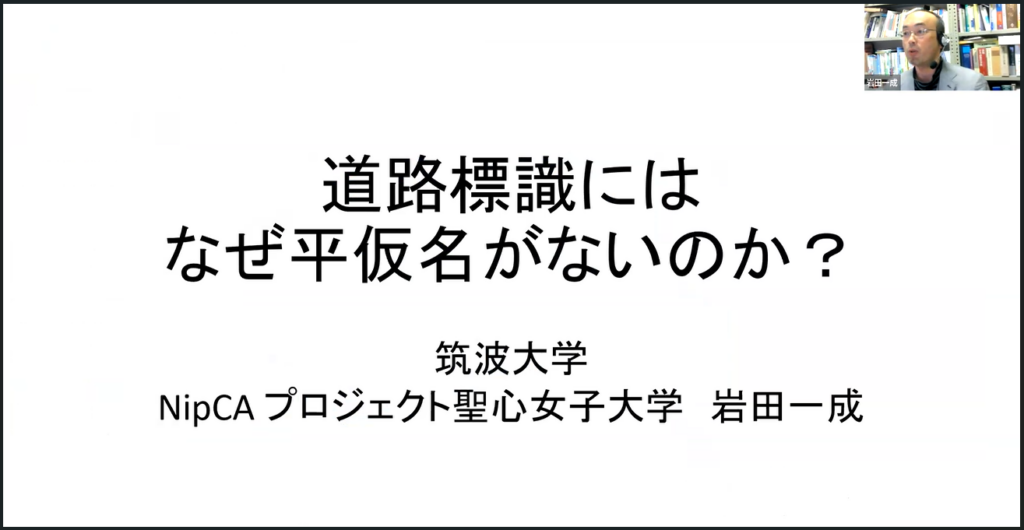2023年12月20日(水)、第46回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催し、聖心女子大学現代教養学部日本語日本文学科教授の岩田一成氏をお招きして、「道路標識にはなぜ平仮名がないのか」と題する講演をしていただきました。
2023年12月20日(水)、第46回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催し、聖心女子大学現代教養学部日本語日本文学科教授の岩田一成氏をお招きして、「道路標識にはなぜ平仮名がないのか」と題する講演をしていただきました。
岩田氏は、日本語教師として青年海外協力隊に参加し、また国際交流基金日本語国際センターなどで勤務されました。さらに、法務省出入国在留管理庁で職員向け研修を行い、同庁の在留支援のために「やさしい日本語ガイドライン」の作成にも関わった実績があります。
講演でははじめに、台湾の公共サインのローマ字表記の種類や、一時避難所ピクトグラムの問題点に関する岩田先生の最新の論文をご紹介いただきました。
つぎに、道路標識におけるローマ字表記の問題をご説明いただきました。調査によると、在住外国人のうち、84.3%が平仮名を読める一方、ローマ字を読める人は51.5%だそうです。また、平仮名は日本人のこどもにとっても最も読みやすい表記です。それにもかかわらず、道路標識はGHQの指令によって修正ヘボン式のローマ字と漢字の併記になっており、平仮名が使われていません。他方、駅名の表示は明治時代からフォーマットが決まっていたため、戦後もそのまま平仮名が使われています。
道路標識のローマ字表記には多くの問題があります。たとえば、sta., stn. (=station) やE. (=east) など、日本の標識には短縮表記があふれていますが、英語話者ですら短縮表記は理解しづらいという調査結果が示されました。ほかに、①同一標識内でさえ「飯田橋」はIidabashi、「神田橋」はKanda Bridge、「二重橋」はNijyubashi Bridgeになるなど、英語とローマ字の混ざり方がまちまち ②在住外国人は英語ネイティブばかりでないにもかかわらず、不必要に難しい英単語が使われる ③長音表記がない場合が多く、その結果、異なる地名が同じローマ字表記になる、等の問題も挙げられました。
また、英語以外の多言語サインが、「警察官立寄警戒中」「防犯カメラ作動中」などの「不愉快サイン」の場合に偏って用いられがちであり、その背後には「外国人=ルールを守らない人」という偏見があるという問題が指摘されました。この改善例として、ピクトグラムのみ、あるいは自分たちの言語である英語のみでサインを記した諸外国の例をご紹介いただきました。
結論として、ローマ字は日本語の音を表示する体系であり、英語訳を表示するものではないこと、また、音声と表記は別物であり、表記には平仮名やローマ字、英語など文字ごとにルールがあることを理解することが重要であるとのことでした。
講演終了後は、道路標識に平仮名を導入していくにあたっての課題や、やさしい日本語の受容をめぐる問題に関する質問、また多くの感想が寄せられ、活発な質疑応答になりました。