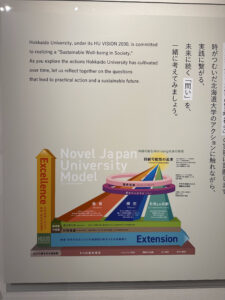オトゥクルベクキジ・アクライ
大学が独自の博物館を持つという考えは、こんなにシンプルで天才的なアイデアなのに、実際はとても珍しい――それが、札幌の北海道大学総合博物館を訪れると知ったときの私の最初の感想でした。
私が最も驚いたのは、その開かれた雰囲気とアクセスのしやすさです。この博物館は、学生や研究者のためだけに建てられたのではなく、好奇心を持つすべての人を歓迎している場所でした。昆虫、鉱物、気候変動、さらには東京の下水道システムに関する展示室もありました。それらを見て、私の毎日の生活を支えている安全な水やインフラ、環境保護などのシステムが、いかに深く学術研究によって支えられているかを実感しました。
まさにこれこそが、SDG 4(質の高い教育)が強調する「包摂的で生涯にわたる学び」の本質だと感じました。そして、誰もが知識にアクセスできることは、強く賢明な社会を築くための一部であることから、SDG 11(住み続けられるまちづくり)とも結びついています。大学が研究を公開するということは、科学と社会のあいだにある壁を取り払う行為です。
また私は、この博物館がいわゆる「象牙の塔」問題――つまり、大学が現実の社会課題から切り離されてしまう問題――に立ち向かっている点にも感銘を受けました。ここでは、研究が生きていて、社会と結びつき、実際の関心事に結びついていると実感できました。
もし、より多くの大学がこの例に倣えば、人々の「教育」に対する見方が変わるかもしれません。教育は単なる学位を取る手段ではなく、日々の暮らしをより良くするための力として捉えられるようになるでしょう。こうした博物館は、公共の対話、学び、そして好奇心を育む空間をつくります。そして、それこそが、より持続可能で公正な未来を築くために私たちが必要としているものなのです。