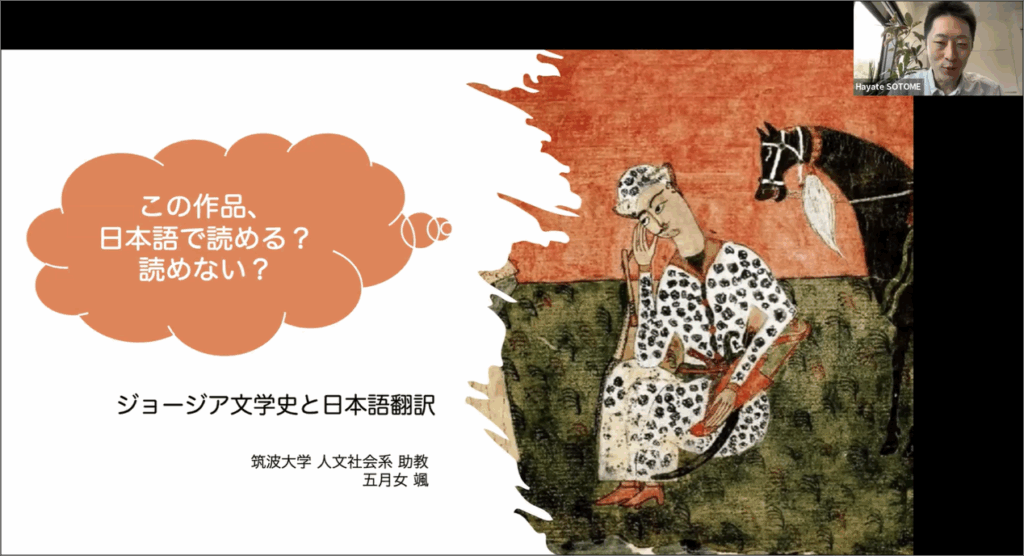2025年5月15日(木)、第54回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。筑波大学人文社会系助教の五月女颯氏を講師にお招きし、「この作品、翻訳で読める?読めない?-ジョージア文学史と日本語訳」と題する講演をしていただきました。
2025年5月15日(木)、第54回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。筑波大学人文社会系助教の五月女颯氏を講師にお招きし、「この作品、翻訳で読める?読めない?-ジョージア文学史と日本語訳」と題する講演をしていただきました。
五月女先生はジョージア文学をご専門とされ、19世紀後半のジョージア文学の二人の作家、詩人を対象に、ポストコロニアリズムやエコクリティシズムといった批評理論を用いた研究に取り組んでこられました。
今回の講演では、古代から現代に至るジョージア文学史の流れを丁寧にたどりつつ、さらに、各時代のどの作家の作品が、いつ、誰によって日本語に翻訳されたのかについてご説明いただきました。
ジョージア文学史は、古代(480年頃)に書かれた聖人伝から始まります。ジョージア最古の文学テクストとされる『シュシャニクの殉教』は日本語訳が存在しないものの、原語のジョージア語で読むと、現代でも意外と理解できるそうです。これは、ジョージア語が日本語ほど大きな言語的変遷を経てこなかったためであると、五月女先生は推察されました。やがて中世に入ると、ジョージア文学の最高傑作『豹皮の勇士』が生まれます。この作品は、ロシア語からの重訳ながら、はじめて日本語に訳されたジョージア文学作品となりました。この訳は、重訳という条件のもとでできる限り原文の意味を忠実に伝えようと、逐語訳調を採用しているとのことです。講演ではさらに、ジョージア文学が近代のロマン主義、リアリズム、モダニズムを経て、現代のソヴィエト文学からポストソヴィエト文学へと展開していく流れ、さらに各時代の作品の日本語翻訳史についても、詳しくご解説いただきました
ジョージア文学は長らくロシア語からの重訳によって紹介されてきましたが、2004年には児島康宏さんがはじめてジョージア語から日本語への直訳を成し遂げました。ここには、1990年代の混乱を経て、2000年代にようやく留学が可能となったという背景があるそうです。さらに2010年代後半以降には、日本語に訳されるジョージア文学作品が増えていきました。こうした動きについて、歴史的出来事と照らし合わせながらご説明いただきました。
講演の最後には、五月女先生ご自身が今後翻訳してみたいとお考えのポストソヴィエト文学の作品やエッセーを紹介され、今後の展望を語ってくださいました。
講演後には、現代ジョージア文学の主要なテーマや、表現の自由について、また訳すことが難しい表現や要素は何かといった点について、質疑応答が交わされました。講演中に触れられなかった児童文学についてもコメントがあり、聴衆のジョージア文学に対する関心の高さがうかがえました。