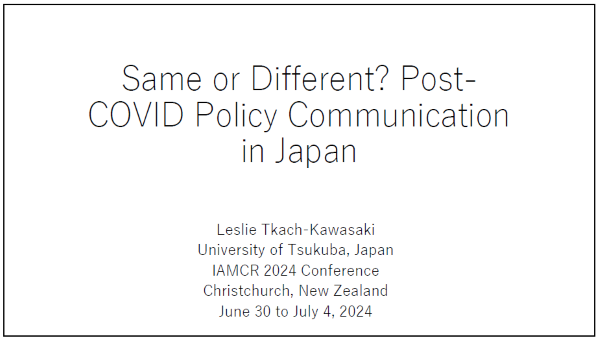日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト(NipCA)のご支援により、筑波大学NipCAフェロー指導教員のタック川﨑レスリー教授が、2024年6月30日(日)から7月4日(木)にニュージーランドのクライストチャーチで開催された国際メディア・コミュニケーション研究学会(IAMCR)2024年次大会に参加し、発表を行いました。
日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト(NipCA)のご支援により、筑波大学NipCAフェロー指導教員のタック川﨑レスリー教授が、2024年6月30日(日)から7月4日(木)にニュージーランドのクライストチャーチで開催された国際メディア・コミュニケーション研究学会(IAMCR)2024年次大会に参加し、発表を行いました。
IAMCRは、メディアおよびコミュニケーション研究に特化した国際的に重要な学術組織であり、1957年にフランス・パリで第1回大会が開催されて以来、長い歴史を持つ国際会議として知られています。年次大会は毎年世界各地で開催され、多様な研究者が参加し発表を行う貴重な機会となっています。学会公式ウェブサイトによると、組織内には17以上のテーマ別セクションと20のワーキンググループがあり、会員は最大3つまで加入することができます(IAMCR2025ウェブサイトより)。IAMCRの年次大会は組織にとって重要なイベントであり、発表数と発表内容の質の双方において高い水準が維持されています。
今回の大会テーマは、「“weaving people together” through “communicative projects of decolonizing, engaging, and listening”(脱植民地化・協働・傾聴というコミュニケーションの営みを通じて、人々をつなぐ)」でした。6月30日の開会式では、地元自治体関係者、IAMCR執行部、開催校であるカンタベリー大学の関係者、その他スポンサーからの挨拶が行われました。開会式は、カンタベリー大学のマシソン・ドナルド教授(地域組織委員会議長)が司会を務めました。また、ニュージーランドのTe Whare Wananga o Awanuiarangi に所属するスミス・リンダ・トゥヒワイ教授が基調講演を行いました。
7月1日、タック川﨑教授は 「Same or Different? Post-COVID Policy Communication in Japan(同一か、異なるか? ポストコロナ時代の日本の政策コミュニケーション)」と題する研究発表を行いました。本研究は、ポストコロナ時代の日本における選挙運動の「デジタルトランスフォーメーション」に着目したものです。日本では、コロナ時代(2020〜2023年頃)に公的分野の多くでオンライン活用が急速に進みました。オンライン選挙運動は2013年の制度改正を契機に本格化しましたが、それまで主に伝統的なオフライン手法に依存していた政治家や行政関係者にとって、コロナ時代はオンライン活用が特に重要な手段となりました。公的サービスのデジタル化が進む中で、オンライン選挙運動は日本の選挙環境において強みと弱みの双方を示しています。
7月3日には、会場内のTe Pae Rivers Roomにて懇親会が開催されました。大会は7月4日の年次総会をもって閉会しました。
最後に、こうした国際会議への参加と研究発表の機会を与えてくださり、世界中の研究者と有意義な議論を行うことを可能にしてくださったNipCAプロジェクトの支援に深く感謝いたします。