カザフスタン医療視察研修で見つけた研究テーマの可能性
医学群看護学類4年 神谷春菜
私は、カザフスタン医療視察研修に参加するにあたり、事前に三つの目標を立てて参加した。そのため、このレポートでは、研修参加の動機に続き、研修での学びや研修前後での成長を記述し、これらの内容を統合して三つの目標の達成度を自己評価することで、自身の研修の成果としたい。
研修参加の動機
私がこの医療視察研修に参加した動機は、中央アジアの文化と医療事情を学び、世界の保健課題への理解を深め、将来的に研究したいテーマを見つけたいと考えたためである。生涯の目標として、世界の健康水準の向上に貢献することを掲げており、地域における課題改善のニーズが高く、解決することで社会全体に効果の大きなトピックを選択したい。そして、私の専門が公衆衛生看護であり、地域保健の環境づくりと実践を担っているため、これらのアプローチで実際に地域の課題解決を促進できるようなテーマを検討したいと考えている。中央アジアは、私自身にとってこれまで全く学ぶことがなかった新たな場所であり、ロシア・ヨーロッパ・アジアに囲まれた地理的にも興味深い地域である。世界から影響を受ける、世界に影響を及ぼす、カザフスタンの保健医療の課題を知り文化や地域特性に合った解決策を検討することは、国際保健に視野を広げ、今後の研究テーマを熟考することに非常に有意義だと考えた。そのため、研修に応募した。
1. カザフスタンにおける保健医療の現状を理解する
渡航以前、研修準備の中でカザフスタンの保健医療について調べを進め、医療人材の国外流出や医療の質、HIVなど感染症の広がりなど複数の課題を持ちながらも、国民皆保険を実現するなど中央アジアの中で先進的に保健医療を推進していることを知った。限られた情報からの考察ではあるが、この段階では、カザフスタンの保健医療は、多くの医療ニーズに対し、質も量も発展途上であるという印象を持っていた。研修を通して、この印象は大きく変化した。アルマティとアスタナの大学や医療施設を見学した際、その高度で最新の医療に驚いた。実際の臨床現場を想定した豊富なシミュレーションセンターや、解剖をデジタルで詳細に確認できる機器など、貴重な教育技術を保持しており、教育の質の高さが伺えた。さらに、学生時代から国内外の大会や学会に参加するような研究やインターンシップを行なっている学生がおり、圧倒された。また、都市には高度な心臓医療やがん治療を提供する病院があり、国内全土だけではなく他国からの医療ツーリズムが盛んであるそうだ。研修中には、数多くの心臓カテーテルの症例を行う先生に話を伺うことができた。カザフスタン南部各地から患者がカテーテル治療を求めてやってくるそうだ。さらに、子どもリハビリテーション病院では、理学療法から音楽療法まで多分野が融合した治療法が提供されている様子を見ることができた。リハビリテーションに使用する義足や補助具の作成まで病院内で行われており、包括的なサービス提供に感嘆した。一方で、総合的な医療サービスを考えると、当初の印象通り、発展途上の状態にあることを実感した。カザフスタンでは2020年に国民皆保険を導入し、すべての国民に公平な医療アクセスを目指し始めたが、その内情は、課題に直面している。医療は基本的に無料であるが、公立病院は待ち時間が長く、人材不足により量も質も十分ではない状態である。また、カザフスタン学生との交流の中で、地域格差の話題が何度も登場し、都心では高度な医療が提供されている一方で、地方では医療にアクセスできない状況が存在していることが分かった。この課題は日本にも共通しており、2. で詳しく理由や解決案について述べる。このように、研修を通して、カザフスタンの医療事情について、インターネットで収集できるデータやコンテンツから印象を想像するだけではなく、具体的なイメージを持って理解することができるようになった。当初の印象から変わった部分も、予想した通りに感じた部分もあったが、実際の医療現場の見学や医療学生の生の声によって、カザフスタンの医療の現状が確かな知識として身についたと感じている。しかし、今回視察した場所はカザフスタンのほんの一部に過ぎず、学生との議論は時間により深く話しきれなかった部分もあった。例えば、個人的には、病院以外の地域の保健サービスの有無やがんのスクリーニングの実施の仕方などについて細かい話を聞きたかったが、積極的に質問することができなかった。したがって、目標1に対する達成度は、80%である。
2. カザフスタンの医療系学生と交流し、グローバルヘルス的な視点で共通の課題とその解決策を議論する
この目標を立てた当初、共有の課題は、世界的な気候変動やパンデミックを予想していた。しかし、実際は、研修中にこれらの課題が取り上げられることはなかった。カザフスタンの学生とぜひこの話題について議論してみたいと考えていたため、自分で交流の機会に積極的に話題に取り上げることができなかったことが反省点である。しかし、研修中の学生交流を通して、次の三点についてよく議論したため、取り上げる。一つ目は、少子高齢化である。日本が25%以上の国民は高齢者といったような超高齢化社会である一方で、カザフスタンでは出生率3.0を維持しており、対照的な状況にある。学生の話によると、新型コロナウイルス後、カザフスタンではベビーブームとなり、さらに子どもが増えたそうだ。実際に、街中でも子どもを多く見かけた。特にショッピングモールで子どもが走り回っている姿が印象に残っている。カザフスタンは例外的に高齢化が進んでいないが、世界では高齢化の傾向にある。この課題に対して、健康な高齢者を増やすといった予防的サービスの充実が議論された。既に日本の多くの自治体では、身体的フレイル予防や認知症予防教室など健康寿命を伸ばす取り組みを行なっているが、今後、世界的に、健康寿命を伸ばすサービスを提供していることが重要だと考える。二つ目は、地域の医療格差の課題である。渡航以前から、カザフスタンにとってこの課題が最も大きな問題ではないか、と予想していた。なぜならば、カザフスタンは非常に国土が広いからである。世界で9番目に大きな国土で、医療を隅から隅まで提供することは非常に困難だと容易に想像できた。実際に、研修の中で、この予想は事実であると学んだ。この課題は、日本においても難解な問題である。縦に広い日本もカザフスタン同様に、地方は医療資源が限られ、都心との医療格差が叫ばれている。学生交流を通して、私は次のような解決案を得た。初めに遠隔医療を発展させることである。地方では医療資源が圧倒的に足りておらず、これが地域格差の主要因であるが、現在、この状況を急激に改善することは難しい。そこで、科学技術を使用して、遠隔医療を普及させ、都心から遠く離れた地方にいても都心の医療サービスにアクセスできるようにすることが最も現実的で効果的であると考える。一方で、実際に対面して診断したり、治療を行ったりする必要があることも多々あり、遠隔医療だけでこの課題を解決することはできない。そのため、地方でプライマリヘルスケアを担う職業を育成することを提案する。現状、カザフスタンでは家庭医(General Practice)が訪問など包括的に地域の医療を見ているが、医師が行う業務が多いため、負担が大きく、サービスの量も質も限られていると推測する。そこで、プライマリヘルス専門の看護師やコミュニティヘルスワーカーなど地域保健に密着した職業を創設もしくは既存の職種を分化し制度を整え、育成を促進することが有効ではないか。一方で、この流れと並行して、医師育成において、地域枠の制度を充実させていくことが重要であると考える。現在、日本、カザフスタンの両国とも、地域枠の制度は既に存在するが、多くの学生が負担に感じる卒後の就業条件や条件終了後の地域への残存率の低さから、継続的に効果を持った制度であるとは言えない。そのため、学生時代の経済的支援と卒後の就業条件のみのプログラムではなく、インドの奨学制度の一つのように、就業条件終了後も、次のキャリアへステップアップできる環境が用意され、その場所でまた奨学金が得られるといったような長期間の連鎖的なプログラムを検討すると有効かもしれない。三つ目に、医療人材不足を挙げる。渡航前には、カザフスタンにおける医療人材不足を深く考えることはなかったが、日本では慢性的に医療人材不足が生じているため、カザフスタンでの似た状況が生じている可能性は想定した。私自身が看護師であり、看護職の労働状況を見るたびに深刻な看護師不足を実感することから、カザフスタンでの看護師の不足については想定通りであったが、甚大な医師不足の現状については、想定を遥かに超えていた。医学生たちの話によれば、医師の仕事は、人の命を預かるため非常に責任感が重く、業務量の多い仕事であるにも関わらず、給料があまり高くないそうだ。そのため、医学生の半数は医学部卒業後に医師ではなくビジネスを行うと話していた。私は、この割合の多さに驚愕した。学校によって、割合に差があると考えるが、医学部生が医師にならないことは重大な課題である。これは、すなわち医学教育の効率が良くないことを意味し、奨学金など国として医学の教育コストが高いことを示唆している。今後、より多くの医学生に医師となってもらうためには、収入の上昇を含めた待遇改善を行うことが大切であると考える。以上より、これら三つのポイントに対する議論を総合して、目標2に対する達成度は、50%である。
3. 中央アジア地域の歴史と文化背景を理解し、保健医療および健康への影響について自分なりに考察する
文化の健康への影響について、①ソ連の影響、②地理的影響、③イスラム教の影響、の三つを挙げる。
①ソ連の影響
カザフスタンは1991年にソ連から独立した。独立以前は、ソ連の保健システムが導入されており、医療は無料であった。しかし、医療制度に対する実質的な権利は、自治体の代表者ではなく政府にあり、医療サービスの量や質をコントロールしていた。独立後、このソ連時代の強制的な保健システムは、人々に大きな影響を残した。それは、ヘルスリテラシーの低さである。例えば、近年、カザフスタンではワクチン忌避が深刻な課題となっている。ソ連時代に、選択肢なしにワクチン接種を強要されていたことから、現在では、ワクチンを打たない選択をする人が多い。この傾向は、子どもの免疫低下や新型コロナウイルスの感染拡大を加速させ、重大な被害を生んでいる。このように、ソ連時代の影響は、ヘルスリテラシーに影響していると考えられる。
②地理的影響
カザフスタンはユーラシア大陸の中央に位置し、国土は砂漠など居住できない土地が多い。また、アスタナは世界で3番目に寒い都市として数えられているように、冬にはマイナス何十度にも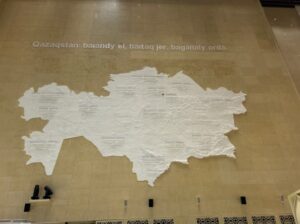 なる極寒地であり、気候が非常に厳しい。これらの影響から、カザフスタン料理は肉がメインであり、その味付けは、長期に保存が効くようにか、塩辛い。さらに、冬場はほとんど全員が車を利用して行動しており、都市部には日中渋滞が広がっている。子どもについて言えば、冬は雪が積もったり、非常に寒かったりと外で遊べないことも予想できる。このような生活習慣は、高血圧や糖尿病のリスクを促進する可能性があると考える。実際に、近年、カザフスタンでは心疾患が主要な死因となっており、糖尿病患者も増加している。学生に聞いた話では、糖尿病の妊婦が増加したことから、巨大児が増えているそうだ。したがって、地理的影響が非感染性の慢性疾患の罹患に影響しているのではないかと推測する。
なる極寒地であり、気候が非常に厳しい。これらの影響から、カザフスタン料理は肉がメインであり、その味付けは、長期に保存が効くようにか、塩辛い。さらに、冬場はほとんど全員が車を利用して行動しており、都市部には日中渋滞が広がっている。子どもについて言えば、冬は雪が積もったり、非常に寒かったりと外で遊べないことも予想できる。このような生活習慣は、高血圧や糖尿病のリスクを促進する可能性があると考える。実際に、近年、カザフスタンでは心疾患が主要な死因となっており、糖尿病患者も増加している。学生に聞いた話では、糖尿病の妊婦が増加したことから、巨大児が増えているそうだ。したがって、地理的影響が非感染性の慢性疾患の罹患に影響しているのではないかと推測する。
③イスラム教の影響
カザフスタンでは、イスラム教が70%以上を占める最大宗教である。イスラム教には様々な教えや信徒としての行動があるが、断食(ラマダン)は特に有名である。今回、医療視察はちょうどラマダンの時期にあたり、案内を担当してくれたカザフスタンの学生をはじめ、多くのイスラム教徒は、日の出から日没まで食事を取らない生活を送っていた。このラマダンについて、客観的に考えると、食生活を1ヶ月のみ劇的に変化させる必要があり、健康に影響を及ぼす可能性があると感じた。日の出から日没の間の空腹を乗り切るために、早起きし、朝ごはんを多めに食べることを予想する。また、日の入り後は、長期間空腹状態の胃に多くの食べ物を一気に食べることを想像する。この食生活の変化は、健康被害を生まないのだろうか。今後、この点について調べてみたい。他方で、イスラム教の女性の生活についての考え方は、女性は自宅で家庭のことを行うべきであるというものである。お祈りもモスクではなく、家で行うことで十分であるとされており、その画一的な考えが伺える。この女性の行動制限について、イスラム教徒の女性たちはこの教えに従うため、自宅で過ごすことが多く、医療へのアクセスを制限することがあるのではないかと考えた。特に、早期発見・早期治療を目的に行われている無料のがん検診は、緊急性がないことから、多くの女性たちは家族から受診する必要がないと判断されるかもしれない。しかし、乳がんは罹患率が最も高く、子宮頸がんも乳がん、肺がん、大腸がんに続き4番目に多いがんである。そのため、女性たちは定期的に乳がんや子宮頸がんのがん検診を受け、がんを早期に発見することが大切である。これらのことから、イスラム教は食生活の変化による慢性疾患のリスクと女性の医療アクセス制限に影響を与えると推測する。
以上の三つの考察を行うことができたため、目標3に対する達成度は100%である。
最後に
研修参加の動機に従い、研修を通して得た研究テーマ案について自分なりにまとめる。研究テーマとしては、「ヘルスリテラシー」に着目したい。その理由は、カザフスタンのように保健システムが発展途上であり、地域医療格差が大きな国でも、国民一人ひとりが予防行動や健康行動をとるようになれば、感染症や慢性疾患のリスクが軽減するからである。国民のヘルスリテラシーが向上し病気を発症することが少なくなれば、医療ニーズは減少する。医療ニーズの減少は、医療現場にゆとりを生み、医療の質を高める動きがしやすくなると考えられる。また、国民のヘルスリテラシーが高くなれば、質の高い医療を求める人が増え、これもまた同様に医療の質を高める流れが促進されると考える。では、具体的にどのようにヘルスリテラシーを高められるだろうか。私は三つのコンテンツを組み合わせた戦略を提案したい。第一段階として、インターネットを使い正しい情報を発信する。カザフスタンのどの地域にいても、どの年代の人でも、同じ質の情報にアクセスできるように、サイトやアプリを効果的に使用することが大切だろう。また、この段階で、同時に、ヘルスリテラシーを普及させる担い手を育成する。日本では保健師がその役割の多くを担っているが、正しい情報を発信するためには、正確な医療知識を持ち、倫理的な情報管理スキルを持つ人材を育てる必要がある。そのため、地域における数十時間のプログラムなど、ヘルスリテラシーを推進する人材育成制度を創設することを提案する。その後、第二段階として、国民の初めの一歩を促すキャンペーンを実施する。例えば、テレビCMやInstagram、YouTubeなどで著名人を起用して、ヘルスリテラシーの獲得を促す。また、必要に応じて、クーポン券などリワードを作る。このように認知度の低い初めの段階で大々的にキャンペーンを行うことで、より多くの人に関心を持ってもらい、カザフスタン全国から正しい知識を獲得していく。この部分がこの戦略の大きなポイントである。今回は、研修で見たものに基づき「推測」と「考察」を行い、提案を考えただけだが、将来、この内容を研究テーマとして膨らませられるように、もう一度内容を再考したいと考える。
研修では、英語でプレゼンテーションを行う貴重な機会をもらったため、それらを振り返る。今までも英語でプレゼンテーションをする経験を何度かしたが、今回のプレゼンテーションは、準備に時間をかけ、カザフスタンの学生との交流と活発な議論を目的としていたため、以前より増して緊張した。1回目は、研修の一番初めの発表であったため、さらに緊張し、原稿を見ずに始め、途中で原稿に戻る必要があっても、原稿の中から必要なパートが見つけられず、内心とても焦ってしまった。また、自分自身が人前で緊張しやすいタイプであるため、プレゼンテーションを行う際には、聞き手に目を合わせないようにしてしまう癖があるが、2回目のプレゼンテーションではあまり聞き手と視線を合わせることなく終えてしまった。スムーズなスピーチのためには原稿が必要であるが、原稿を読むだけでは、相手に伝えたい内容が伝わらないまま終わってしまう。そのため、次回の機会には、初めに原稿を用いて何度も反芻してスムーズなスピーチを練習し、ある程度暗記できたら、原稿を見ないで聞き手の方を見て伝わるように話すというような二段階の練習をしたいと考える。













